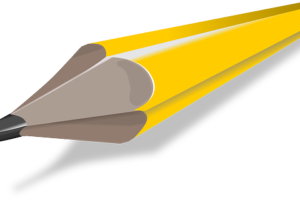Warning: Undefined array key 6 in /home/schlicht/sunao21schlicht.com/public_html/wp-content/themes/jstork_custom/functions.php on line 54
Warning: Undefined array key 6 in /home/schlicht/sunao21schlicht.com/public_html/wp-content/themes/jstork_custom/functions.php on line 54
卒論のテーマをどうやって探せばいい?
こんにちは、すなおです。
日本大学通信教育学部の文理学科は卒業するにあたって卒業論文の提出が必須となります。
当方は2020年末に提出することができましたが、最初は何を書けばいいのかわかりませんでした。

という方に向けて当方が考えたこと、やってきたことを今回ご紹介したいと思います。
ちなみに当方は史学専攻の卒業論文を執筆したので他の学科・専攻の方はズレがあるかもしれませんが、「こんなもんか」程度で読んでいただければ幸いです。
スポンサードサーチ
目次
卒業論文って何?
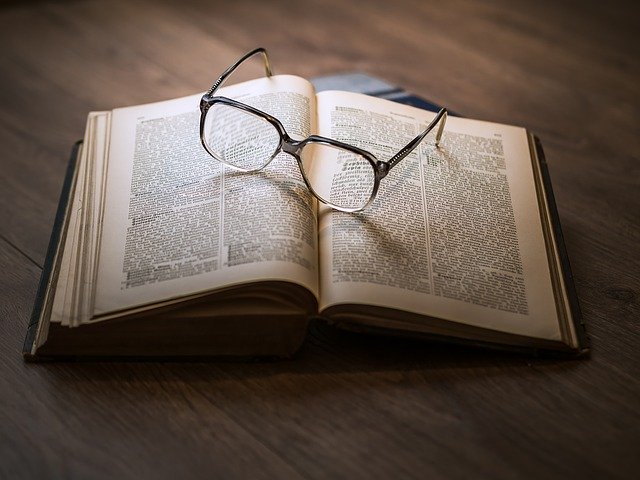
日大通信で配布される卒業論文作成の一般的注意事項(三訂)によると↓
卒業論文とは、歴史上のできごとを研究対象にし、歴史学の研究方法にもとづいて資史料を集め、分析・考察し、新しい歴史事実を見出したり、新たな解釈を加えて作成するものです。先行研究の成果や課題を理解すること、方法論を身につけることが大切です。
とされています。
超ザックリとまとめると、すでに別の研究者に発表された資料Aと資料Bに、これまで誰にも利用されていない資料Cを加えることで新しい仮説(視点)が生まれる認識でいいです。
なので分野やテーマによって異なりますが、完全オリジナルの論文を執筆する必要はありません。
極論を言ってしまえばいくつかこれまで誰にも利用されていない資料(データ)を見つけて活用すればほぼ完成みたいなもんです。
これを聞けば若干気が楽になったりしませんか?
テーマ設定:ルールは絶対に守る。
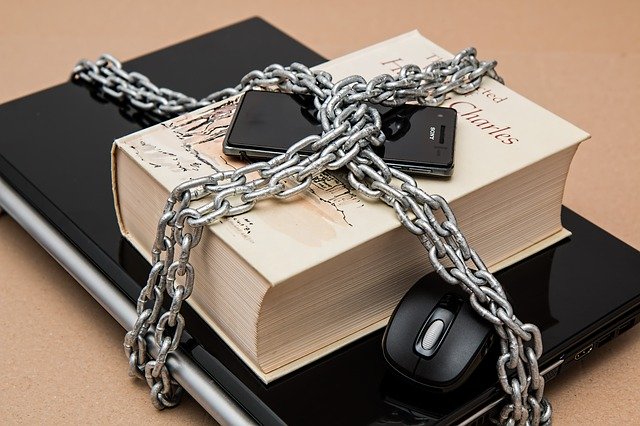
卒業論文を研究、執筆するうえでこれは絶対に守らなければなりません。
執筆した卒業論文をただ書き上げれば言いわけではありません。最終的には教授が提出された卒業論文をチェックし、合否を決めます。なのでその教授のやり方に逆らう方法で執筆していくのは絶対に不合格になります。
また、論文と言う形式で執筆しなければいけないので、論文の書き方(ルール)に則っる必要があります。
日大通信で配布される卒業論文作成の一般的注意事項(三訂)によると↓
11冊の書物や論文のあらすじや要旨をまとめたものは論文ではありません。
2他人の説を無批判に繰り返したものは論文ではありません。
3歴史資料の引用を並べただけでは論文ではありません。
4歴史資料で実証されていない思い込みや私見では論文にはなりません。
5他人の研究業績やアイデアを無断で使ったものは「盗作」となります。
以上のルールを絶対に守りましょう。
また、教授によってはさらに細かいルールを求めてくる場合があるので、下手に逆らわずに守りましょう。
スポンサードサーチ
テーマ設定:卒業論文のテーマを決める。
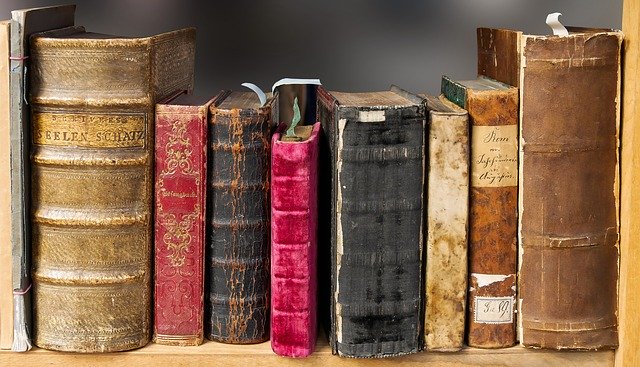
ではこれまでの前置きをこれまでとしてテーマ設定の一連の流れを解説します。
ルールを理解できれば卒業論文のテーマを決める必要があります。
卒業論文のテーマ決めは超重要な行程です。卒業論文の作業の行程の半分を占めていると言っても過言ではありません。
ではどんな手段を用いてテーマを探せばいいかを以下の箇条書きで紹介していきます。
- 興味ある分野の概要が書かれている本を探し、一通り読んでみる。
- その中で気になったテーマを見つけたらさらに深掘りされた本を探し、一通り読んでみる。(無理そうと感じたら最初に戻る↑)
- 深掘りされた本が参考している資料を探す。(無理そうと感じたら最初に戻る↑)
- 自分でも書けそうと感じたら、テーマとして設定する。
以上の行程を少し掘り下げて行きます。
1.興味ある分野の概要が書かれている本を探し、一通り読んでみる。

と考えている方も中にはいらっしゃいますが、中には当方みたいに何も考えていなかった場合もあるかと思います。
しかし、これまで講義を受けてきた中で疑問に思ったこと、気になったことが多少なりともあったかと思います。
その分野についての概要が書かれている書籍があると思いますのでその本を入手して一通り読んでみることをお勧めします。今まで学んだことについて軽く復習する程度の気持ちで読んでみると今まで興味がなかったテーマにも興味を持ったりするので損は少ないかと思います。
2. 気になったテーマが深掘りされた本を探し、一通り読んでみる。
概要書籍の中で気になったテーマを見つけた場合、そのテーマが深掘りされた書籍・論文を読んでみることを勧めます。
分野によりますが複数の書籍・論文をインターネットなどでみるけることができると思いますのでしっかり読まなくてもいいので一通り目を通しておきましょう。最悪、書籍の目次だけでもいいです。
もし思っていたのと違うと感じたら諦めて別のテーマを探しにいきましょう。卒業論文の完成はかなり時間がかかるので時間の節約ですね。
3. 深掘りされた本が参考している資料を探す。
好感触がつかめたら初めて書籍・論文をしっかり読んでみましょう。
その書籍の巻末などに参考・引用した書籍、資料(データ)が記載されているので今度はその資料を入手してみましょう。
オーソドックスな手段は図書館やインターネットだと思いますが当方が勧めるのは東京と大阪にある国会図書館がお勧めです。理由は以下です。↓
- 所蔵数が多いのでマイナーな本もある可能性が高い。
- オンラインで本を探すことができ、閲覧の予約ができる。
- 複写したいページ数が分かっていれば家で複写を頼める。
便利な機能を最大限使っていきたいですね。
4. 自分でも書けそうと感じたら、テーマとして設定する。
ここまで進められれば、テーマ設定の完成です。頑張っていきましょう。
テーマ設定:卒業論文テーマ設定の注意点

これまでテーマ設定の大まかな流れを紹介しましたが、うまくいかない人もでてくるかと思います。
「こんな状況だと卒業論文を執筆するの大変だよ」というパターンがあるので紹介していきます。
設定したテーマの対象が狭すぎる

と強く持っている人にありがちなパターンです。
当方は史学専攻なので歴史を例に出しますと、とある人物についての卒業論文を執筆することにしたと仮定します。
最初から「ある人物」という限定されたテーマ設定しますと、万が一の卒業論文の軌道修正が困難になります。
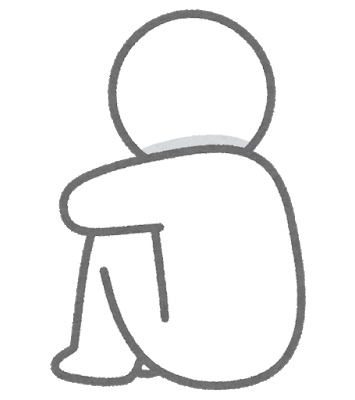
という状況も十分にあり得ます。
なので最初からシッカリ決め過ぎずに万が一軌道修正することになってもなんとか対応できるような体制をととのえていくことが大事です。
テーマがマイナーすぎる
研究対象がメジャーなものがあれば、マイナーなものがあります。
マイナーになるにはマイナーになってしまう理由があります。
- そのそも資料(データ)が少ないor無いから。
- 他の研究者が研究していない分野で認知度が低いから。
私たちは学生である以上、完全なオリジナルの論文を書く必要はありません。
門外不出の誰も使われていない資料があれば執筆してもいいかもしれませんがそんなものは誰もが持っているわけではありません。
「卒業論文を提出し卒業する」ことを目的に据えるのであれば資料があり、他の研究者が論文や書籍を出している分野をテーマにすることを勧めます。
また本決まりする前に教授に相談してみることを強く勧めます。
その分野についてのプロである教授に事前に相談しておくことで色々と教えてくれたりとご自身を助けてくれるので連絡を取れるのであればこまめに連絡を取手っていきましょう。
スポンサードサーチ
最後に
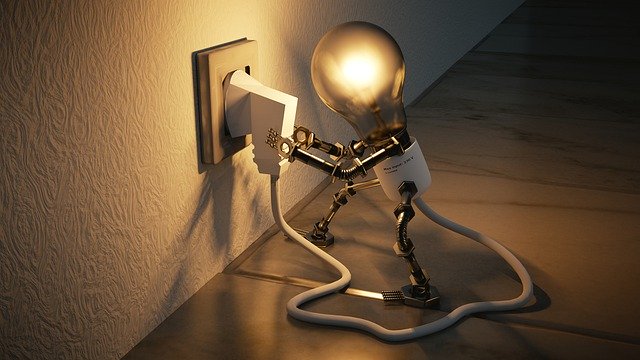
いかがでしたでしょうか?
卒業論文のテーマを設定する際にどうやって進めていけばいいかなんとなくでも分かっていただけたら幸いです。
しかし、今回このように紹介しましたが、まずは教授の言っていたこと、ルールを守ることが第一です。合否を出す立場の人に逆らうのはご自身の成績に悪影響を与えるのはよくないですからね。
卒業論文はとにかく時間がかかります。
できるだけ早い時期からいろんな本を読み、テーマ設定のことを考えておくと後々楽になりますよ。
じゃ、また!